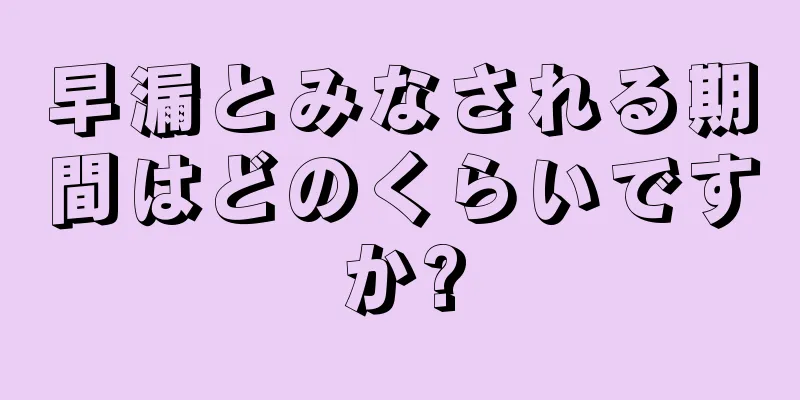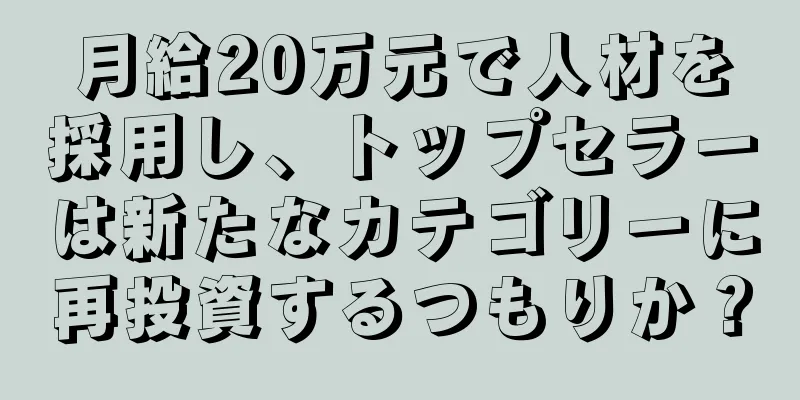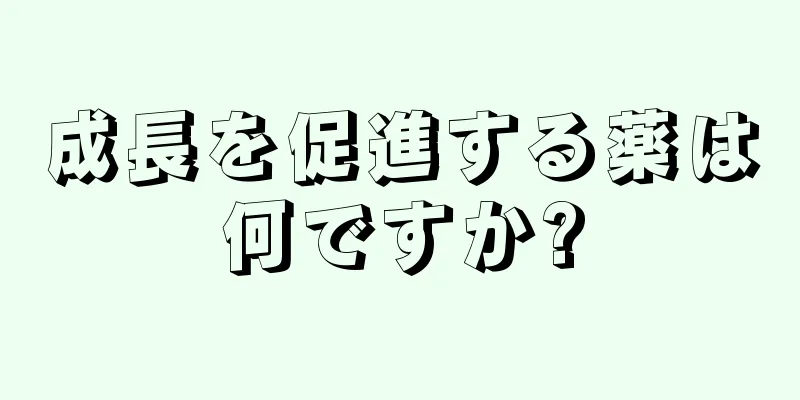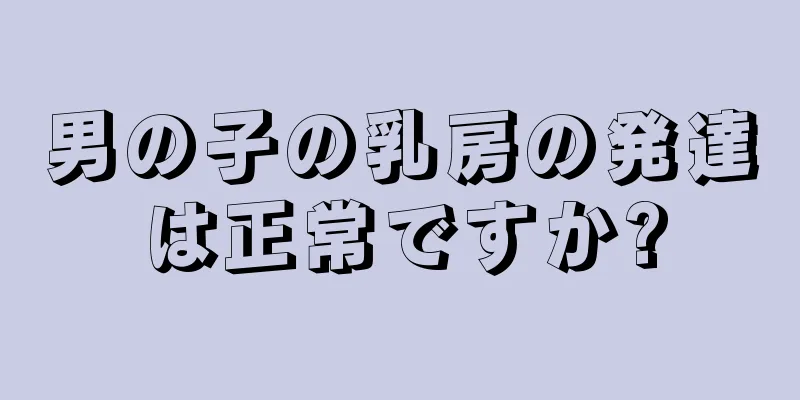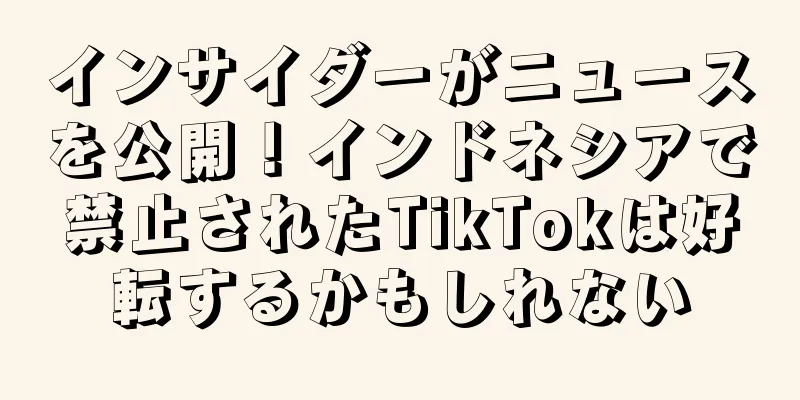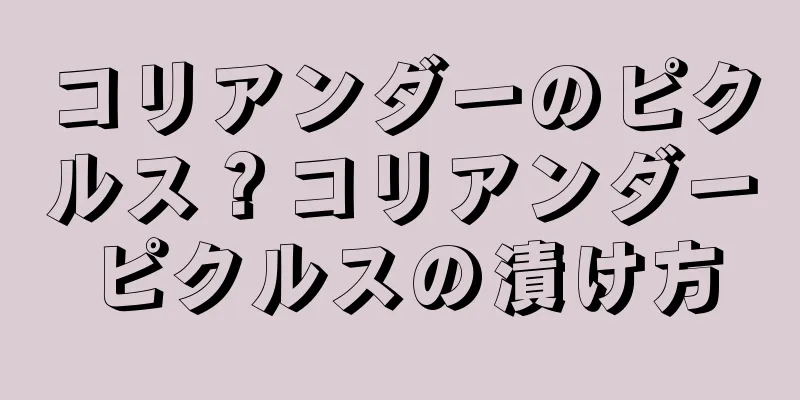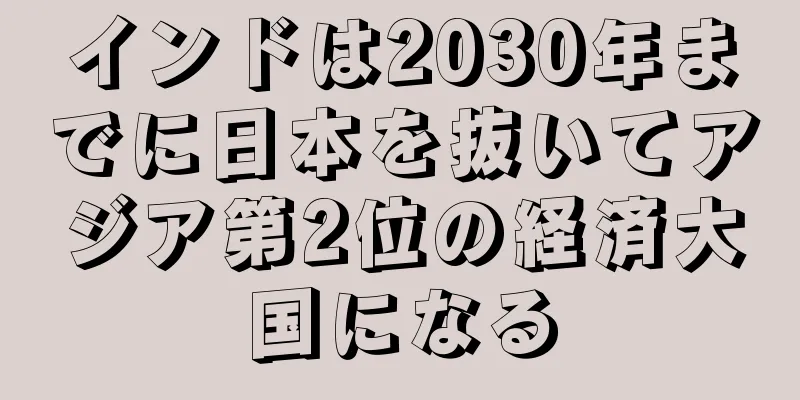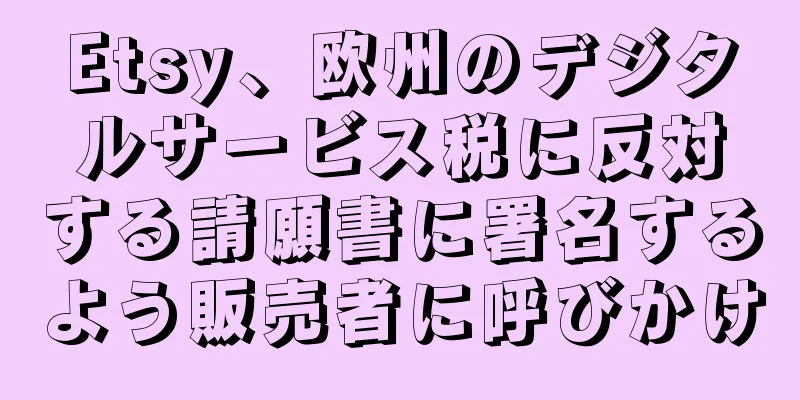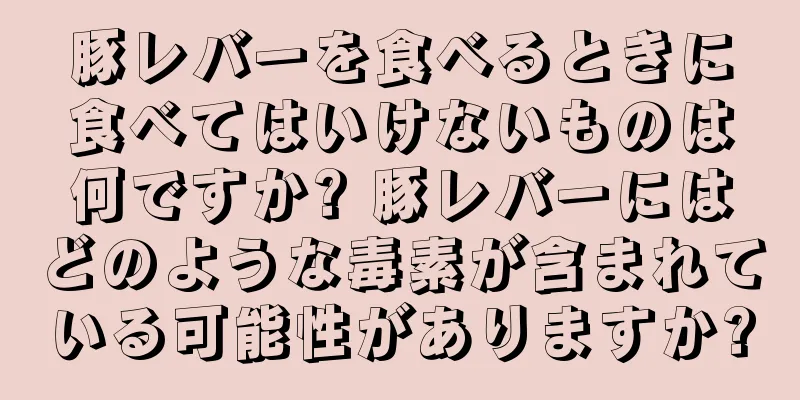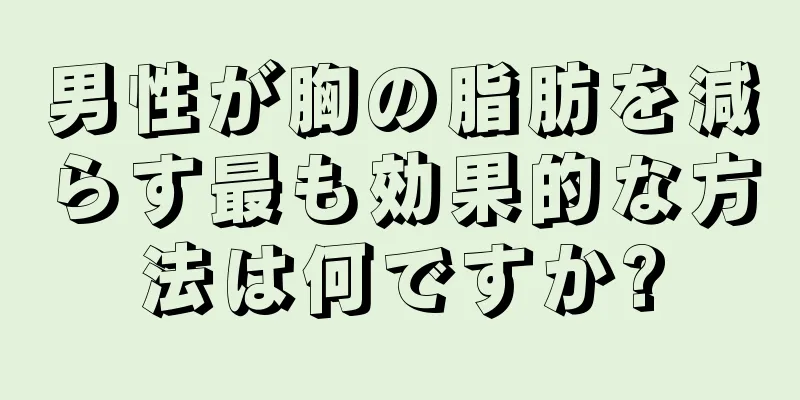週3回の射精
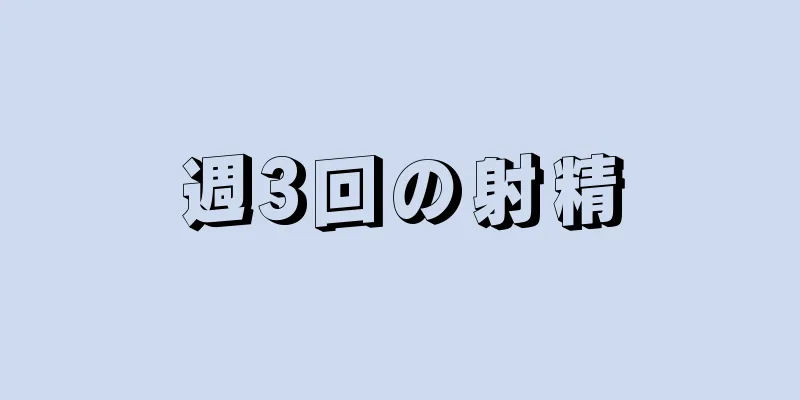
|
男性の性に対する要求は常に女性よりも高く、人間の本能により、男性は性機能も強いです。しかし、男性があまりに頻繁にセックスをすると、射精しすぎて体にダメージを与え、ひどい場合には性機能に大きな影響を与えます。そのため、男性は性生活の頻度を適度にコントロールする必要があります。では、週に3回射精するのは多すぎると考えられますか? 射精の頻度については、簡単な公式(99射精表)があります。 週に何回が普通ですか? 年齢(最初の数字)×9、例えば60代の場合は6×9=54となり、5週間ごとに4回行うことになります。70代の場合は7×9=63となり、6週間ごとに3回行うことになります。週に何回やらなければなりませんか? 2x9=18==>20歳。週8回の射精 3x9=27==>30歳。 2週間ごとに7回の射精 4x9=36==>40歳。 3週間ごとに6回の射精 5x9=45==>50歳。 4週間ごとに5回射精する 6x9=54==>60歳。 5週間ごとに4回の射精 7x9=63==>70歳。 6週間ごとに3回射精する 8x9=72==>80歳。 7週間ごとに2回射精する 9x9=81==>90歳。 8週間に1回の射精 過度なセックスが体に与える6つの主な害 誘発性性機能障害 男性が頻繁に性行為をすると、2 回目の射精は 1 回目よりも確実に長くなるため、射精時間が長くなります。これにより、将来的にインポテンツ、無射精、射精遅延、性生活の喜びの欠如などの性機能障害を引き起こすという隠れた危険が生じます。 体調が悪化する 男性にとっても女性にとっても、それは大きな肉体的疲労を引き起こし、時間が経つにつれて必然的に体調不良につながります。すると精神状態に影響を及ぼし、思考力、記憶力、分析力までも低下してしまいます。 複数回使用すると満足度が下がる 男性、女性を問わず、性交を繰り返すと、2回目、3回目、4回目の性交時の性的満足度が前回よりも低くなり、心理的な影響を受けやすく、性的能力に問題があると考え、最終的には心理的、精神的要因による性機能障害につながります。 長期間の無反応期間 男性は性交後に無反応期間を迎えます。つまり、性交後のある一定期間は性的刺激に反応しなくなります。頻繁かつ繰り返し性交を行うと、無反応期間が長くなり、性機能障害につながりやすくなります。 腰痛を悪化させる 男性が頻繁に性行為をすると、性器の鬱血が繰り返し起こり、前立腺炎や精嚢炎などの病気を引き起こす可能性があり、会陰部の不快感や腰痛だけでなく、血精液症も引き起こします。女性が性交を頻繁に繰り返すと、性器が常に鬱血状態になり、骨盤内の鬱血、いわゆる骨盤鬱血症候群を引き起こし、腰痛や下半身の重だるさなどの不快感を引き起こします。 性器の「過労」 性衝動が継続的に繰り返し発生すると、男女ともに性制御中枢と性器への負担が増加し、頻繁な疲労の結果は予想に反し、性機能の低下を引き起こし、性機能の「早期老化」につながります。 |
推薦する
男性における腎虚と血液うっ滞の症状は、これらの症状が最も一般的です
男性の友人は、めまい、耳鳴り、不眠症、便秘、腰痛、頻尿、風邪への恐怖などの症状があるかどうかを確認す...
頻繁な夢精は身体にどのような害を及ぼしますか?
頻繁な夢精のデメリットは何ですか?頻繁な夢精とは、性交により夜間に精液が自然に放出される症状を指しま...
思春期の男性が頻繁にこれにぶつかると、腎臓が破壊されてしまいます。
ベジタリアンが流行する昨今、健康志向の男性の間では、栄養価が高く太りにくい大豆製品を肉の代わりとして...
男性はなぜ性器が膨らんでいるのでしょうか?
人生において、女性は多くの性器の問題を抱えるでしょうし、男性も多くの性器の問題を抱えるでしょう。男性...
蜂蜜は男性の性機能を改善できますか?
多くの男性は性機能に問題を抱えており、パートナーの前で堂々とした態度を取れないほどです。深刻なケース...
亀頭洗浄に過マンガン酸カリウムを使用しても大丈夫ですか?
亀頭炎といえば、確かに男性にとっては話しにくい病気です。結局のところ、それは男性の生殖器官の問題...
包皮切除後にペニスにしこりができる原因は何ですか?
包皮炎はよくある病気です。包皮炎の場所は非常にプライベートなため、多くの男性は恥ずかしくて病院で治療...
Wishが「Wish入門」ビデオシリーズを開始、CEOが変革プロセスの最新動向を共有
北京時間7月1日、世界的なモバイル電子商取引プラットフォーム「Wish」の親会社であるContext...
手首骨折の後遺症を防ぐためには、これらのことに注意しましょう!
手首の骨折は肉体労働に従事する人にとって最もよくある事故です。早めに病院に行って治療を受けたとしても...
男性の尿道から透明な粘液が流れる場合の症状は何ですか?
生殖器疾患や泌尿器疾患によっては、男性の尿道から粘液が出ることがあります。粘液の見た目から、どのよう...
軽度のうつ病を治療し、緩和する方法
病気によって見分け方は異なり、うつ病も軽症と重症に分けられます。うつ病の程度が異なれば、患者には異な...
睾丸の皮膚のかゆみを治療する最善の方法は何ですか?
男性にとって、睾丸の皮膚のかゆみは、特に若い男性にとって非常に一般的な現象です。この症状の原因は非常...
歯磨き粉が男性に与える魔法の効果とは?
歯磨き粉は日常生活にとても役立ちます。日常生活で歯を磨く以外にも、歯磨き粉にはたくさんの小さな用途が...
男性の腎臓に栄養を与えるのに最適な食べ物は何ですか?
社会的圧力が増すにつれ、男性はますます自信を失っていきます。これは仕事だけでなく、人生にも反映されま...
亀頭が紫色なのはなぜですか?
亀頭が紫色に見えるのは正常で、これは主に亀頭の血液の蓄積と生理的反応によるものです。男性のペニスが刺...