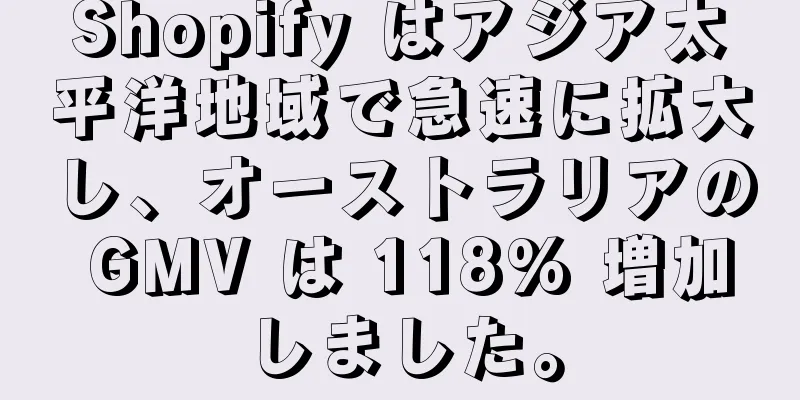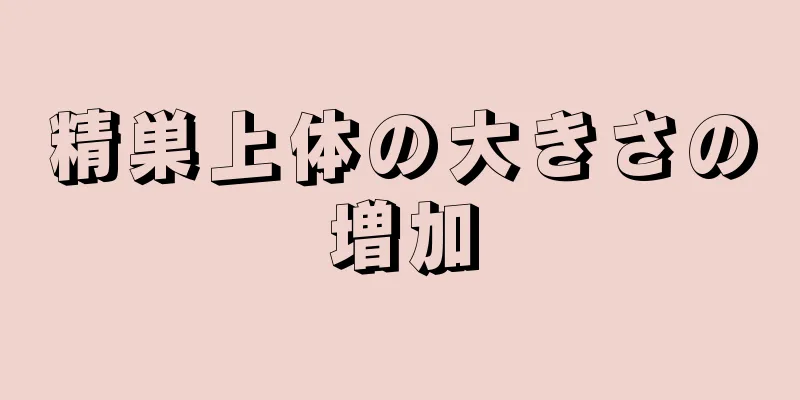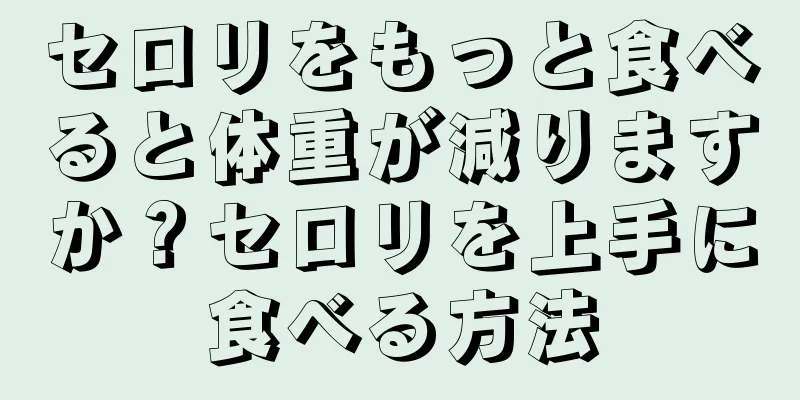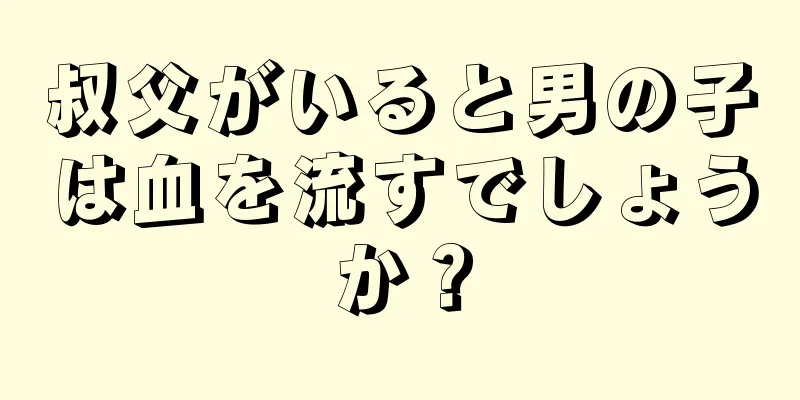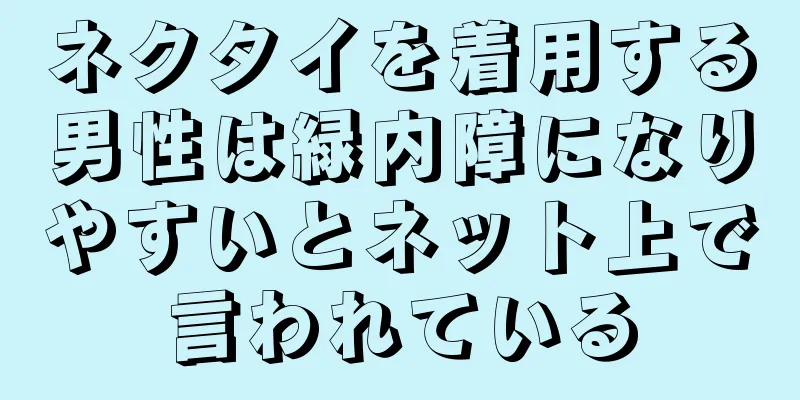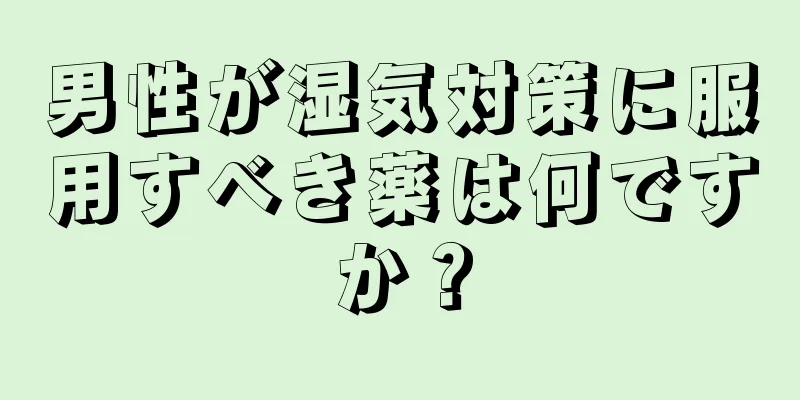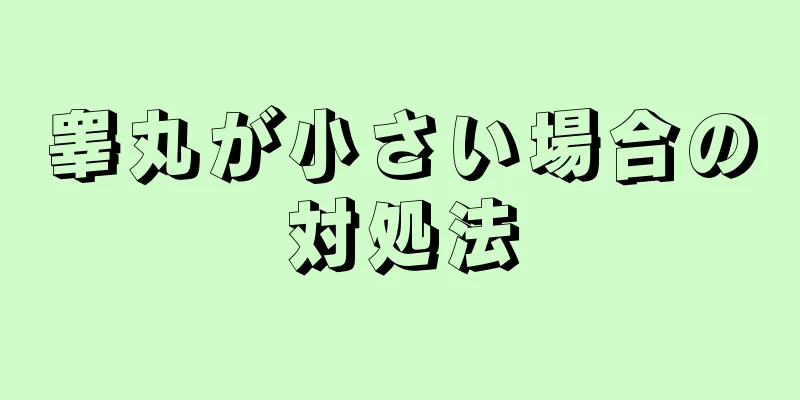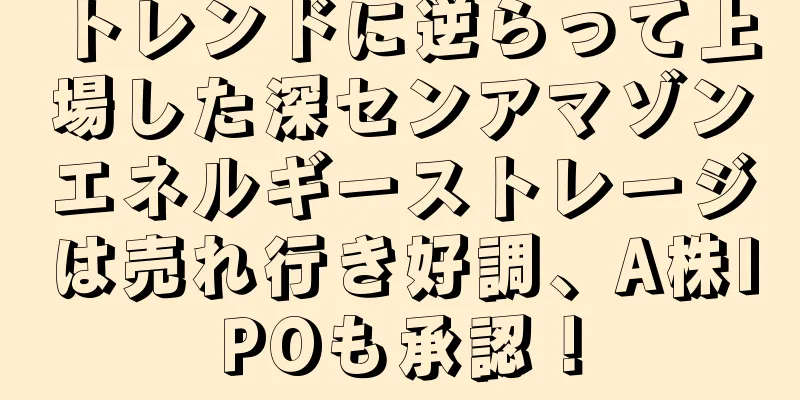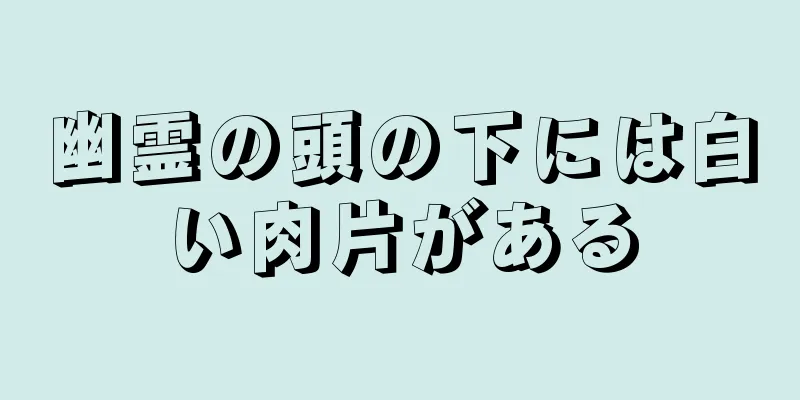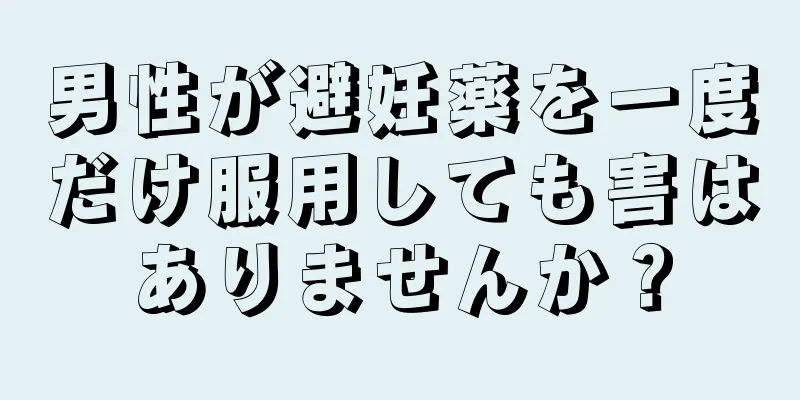左睾丸下垂の原因
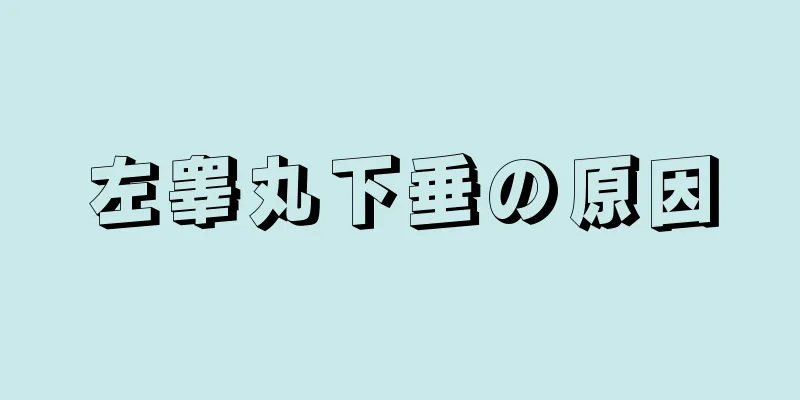
|
男性の睾丸は生殖器官として非常に重要です。睾丸の最も重要な点は、子孫の生殖であると考えられていることです。睾丸がなければ、男性は妊娠することが非常に困難です。多くの場合、男性は睾丸の垂れ下がり現象があると感じることがよくあります。睾丸は2つあり、1つは左、もう1つは右にあります。多くの場合、男性の睾丸の1つだけに問題があります。多くの男性は、左の睾丸にこの垂れ下がりの症状があると言います。では、左の睾丸の垂れ下がりの原因は何でしょうか? 1. 精巣炎。男性が精巣炎を患うと、ひどいたるみを引き起こす可能性があります。患側の睾丸を検査すると、皮膚の赤みや腫れ、睾丸の肥大、顕著な落下感、圧痛などが認められることがあります。 2. 精索静脈瘤。精索静脈瘤が発生すると、陰嚢の中にミミズのような血管の突起が現れ、精巣が正常に垂れ下がることを誰もが知っておくべきだと思います。さらに、精索静脈瘤は陰嚢の腫れ、局所的な重さ、明らかな痛みも引き起こしますが、これは疲労によって引き起こされることが多く、時間の経過とともに病気を悪化させます。症状は横向きに寝ているときのみ緩和されます。 3. 前立腺炎。前立腺炎に問題がある場合、異常な精巣の垂れ下がりが起こり、その他の症状として尿意切迫感や排尿時の痛みなどが現れることがあります。 静脈瘤のため左の睾丸が垂れ下がっています。静脈瘤とは、精索の静脈還流の閉塞、弁の機能不全、血液の逆流による血液の停滞、静脈叢の拡張、伸長、屈曲につながる状態を指します。95% は左側に発生し、両側に発生することはまれです。多くの人は、精索静脈瘤が精子形成や精液の質に影響を及ぼし、不妊症を引き起こす可能性があると考えていますが、外科的治療によって生殖能力が回復する人もいます。この病気は一般男性人口の約 20% に発生し、不妊男性の約 40% に発生します。この病気は若い男性や中年の男性に多く見られ、思春期の若者には比較的まれです。6~19歳の青年における静脈瘤の全体的な発生率は10.76%ですが、その程度はより重篤で、ほとんどがグレードIIIです。 原発性静脈瘤 静脈瘤の原因は主に精静脈の血液の鬱血によるもので、人の直立姿勢は精静脈の還流に影響を与えます。静脈壁と周囲の結合組織の弱さ、または精巣挙筋の発達不全。静脈バルブは不完全に閉じているため、最近の静脈瘤が発生しやすいです。左側のINSは、左の精子が右側よりも約8〜10 cmであるため、左腎静脈が大腸に圧縮される可能性があります。 ;右の一般的な腸骨動脈は、左の腸骨静脈を圧縮し、左の精子静脈の戻りを妨害し、いわゆる遠位「クランプ」現象を形成します。 以上が精巣下垂の原因の紹介です。左の精巣が下垂し始めたら、注意が必要です。精巣炎であれば、男性に大きな害を及ぼします。静脈瘤であれば、男性不妊の可能性が非常に高くなります。早めに検査し、必要に応じて手術を受ける必要があります。片方の精巣を切除しても、生殖能力には影響しませんので、心配しないでください。 |
推薦する
男性の頭頂部の脱毛の原因は何ですか?
実際、男性が脱毛の問題を抱えると、非常に恥ずかしい思いをすることがよくあります。そして現在、さまざま...
牛! 1000株以上が突然放棄され、売り手は補償を請求し22万株を取り戻した。
Amazonでの競争は激化している。一つの兆候としては、ラストマイル配送料を節約し、価格競争力を高...
アマゾンの新アルゴリズム誕生、越境サークルは「再編」されるのか?
最近、Amazon のチームが Amazon Science で関連レポートを発表したため、Amaz...
毛穴を引き締める方法、男性が毛穴を引き締めるコツ
毛穴の開きは女性だけの問題ではありません。男性も同じ問題を抱えている人が多くいます。実は、男性のスキ...
大雨と洪水により、ポート・クランの物流は深刻な麻痺状態に陥っています。
外国メディアの報道によると、マレーシアは最近、激しい大雨に見舞われた。ポート・クラン当局は、局地的な...
陰嚢液漏出の原因は何ですか?
男性精巣水腫は、精巣を囲む膣腔内に正常量を超える液体が蓄積することで起こる嚢胞性疾患であり、症状のあ...
亀頭疣贅の初期症状は何ですか?
日常生活において、男性は生殖器の周囲の清潔さと掃除に注意を払う必要があります。そうしないと、亀頭疣贅...
陰嚢注射法
男性の陰嚢は非常に敏感な部分だということは誰もが知っています。また、炎症やその他の問題を引き起こすこ...
このトラックは非常に人気があり、今年の初めには数千万ドル相当の資金調達が 2 件ありました。
1月中旬だけでも、このブルーオーシャントラックはすでに数千万元相当の資金調達を2件確保する先導役を...
ピークシーズンが延長?アメリカの買い物客のほぼ半数がクリスマス後に買い物をします。
新たな調査によると、ほとんどのアメリカ人消費者がホリデーショッピングをまだ終えていないことが分かった...
男性にとって、過剰な恥垢はどんな害をもたらすのでしょうか?
男性の包皮の長さは身体の健康に大きな影響を与えるため、男性は良好な個人衛生を維持する必要があります。...
男性の右耳が熱くなる兆候は何ですか?
誰もが耳が熱いという症状を経験したことがあると思いますが、説明のつかない耳の熱さに関する民間言い伝え...
豚足と豆のスープを食べることによる男性への影響
豚足と大豆のスープは栄養価が高く、豚足と大豆が栄養豊富な食品であることは誰もが知っています。豚足には...
前立腺炎の診断検査は何ですか?
前立腺炎はよくある病気です。患者は泌尿器系の症状を経験することが多く、会陰部に不快感を引き起こす可能...
セックス時間を増やすためのエクササイズ
男性がセックスの時間を長くしたいなら、体の栄養状態を改善することに注意し、食事の構造を適切に計画し、...